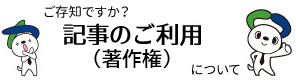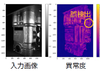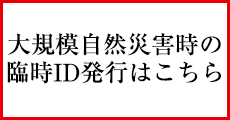(2020/4/2 05:00)

「夜に入り候へて降り候砂の色黒く(中略)昼夜降り候砂、およそ二、三分ほど積もり申し候」―富士山の『宝永噴火』(1707年)の観察記録を当時の旗本、伊東祐賢は『伊東志摩守日記』に記している。噴煙は偏西風に乗って東方へ広がり、江戸市中は数センチメートルの降灰に覆われた。
政府の中央防災会議の作業部会は、宝永噴火と同規模の噴火が起きれば除去が必要な降灰は約4・9億立方メートルに上るとの試算を示した。東日本大震災で出た災害廃棄物の約10倍にあたるというから、被害は尋常ではない。
視界不良による交通渋滞や航空機の減便、火力発電所の稼働停止、通信網の寸断などで、首都圏はまひ状態に陥る危険性がある。現時点で噴火の兆候はないが、万が一に備え、自治体やインフラ事業者は防災計画を作る必要があるとしている。
桜島の噴火に悩まされている鹿児島市の対策は参考にしたい。商店街を対象に手押し式降灰除去機の購入費用や、降灰が下水道に詰まった時の除去費用の一部を行政が補助している。
300余年静穏を保ち、世界文化遺産に登録された秀麗な富士が、自然の牙をむいて我々に襲いかかる光景は信じがたいが、感染症と同様、人知を超えた自然の怖さは侮れない。
(2020/4/2 05:00)