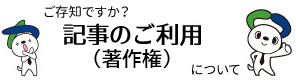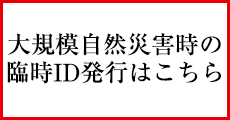[ オピニオン ]
(2019/5/14 05:00)
国立大学の改革を象徴する統合の計画が、名古屋大学と岐阜大学など4件で進んでいる。文部科学省が準備する「1法人複数大学制度」なら、今の各大学の独立性と統合による効率化を両方できるためだ。しかし、リストラは難しいなど企業と異なる点も多い。統合の言葉に踊らされない意識も必要だ。
国立大の2004年度の法人化から15年たち、各大学の意識は自ら選んだ主な方向性「地域」「特色」「世界」などで変化してきた。大学の個性を生かすのに、文部科学省が打ち出した新たな法人形態がはまり、統合の流れとなった。具体的には名大・岐阜大(実施目標は20年度)のほか、静岡大学と浜松医科大学(21年度)、小樽商科大学と帯広畜産大学、北見工業大学(22年度)、奈良教育大学と奈良女子大学(同)の4件だ。
1大学で不足する部分を補う大学連携は、近年かなり増えている。文理融合の東京の4大学連合や、伝統の医学部の“旧六”グループの6大学など、活動年数を重ねたケースもある。北海道で統合を計画する小樽商大の和田健夫学長は「参考にすべきものは多くある。統合に向けて出てくるさまざまな課題は、克服できると信じている」と強調する。
統合は一般に、企業合併のように格段の経営効率化の手段とされる。しかし、国立大の場合は準公務員的な人事制度で動いてきたため、即時の人員削減ができない点で注意がいる。法人化前後に実施された統合例もそうで、「総合大学による単科大学の吸収で、同様の部局の重複をうまく解消できなかった」(内閣府関係者)との話も聞く。
もちろん「財務や人事などは統合による効率化が見込める。それにより研究支援や外部資金獲得の専門人材を強化するなどの戦略が立てられる」(文部科学省高等教育局の国立大学法人支援課)ということは期待できる。社会的な必要性が薄れた分野などの再編も、統合を機に進んでいくに違いない。何をするのか、どのような効果を引き出すのか。統合のその中身を注視していきたい。
(2019/5/14 05:00)
総合2のニュース一覧
- 温室効果ガスに新算定法、水素製造も対象 IPCC報告書(19/05/14)
- 2019中小白書を読む(3)IT活用し商機創出(19/05/14)
- 社説/国立大の統合計画 課題を含め中身に注視を(19/05/14)
- 政府・イノベ会議、産学共同研究で新法人 正式発表(19/05/14)
- 政府、増税再延期に慎重 経済対策には含み(19/05/14)
- 株、6日連続下落 153円安 米中貿易摩擦を懸念(19/05/14)
- メガソーラー、環境アセス対象へ意見公募 環境省(19/05/14)
- 増田文彦氏(マスダック創業者・元社長)のお別れの会、しめやかに(19/05/14)
- 【おくやみ】柳沢久仁夫氏(シナノ産業社長)(19/05/14)
- 【おくやみ】高田哲男氏(元旭化成工業〈現旭化成〉副社長)(19/05/14)
- 企業信用情報/9日・10日・13日(19/05/14)