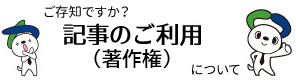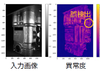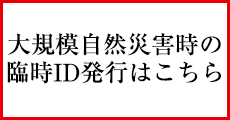[ トピックス ]
(2016/8/4 05:00)
■官民連携で推進■
イノベーションで日本を成長軌道に導くビッグプロジェクト「ソサエティー5・0」が動きだす。経済界は「日本版第4次産業革命」を「ソサエティー5・0」と称し、自社の技術やノウハウを快適な社会の実現に生かす構えだ。課題先進国・日本ならではの新たな社会インフラ輸出としても期待され、官民一体で新潮流を生み出す。
■日本を成長軌道に導く■
【理想の日常】
20XX年のある休日。都内在住のA氏が訪ねるのは郊外に暮らす70代の母親だ。日々の健康データは医療機関と共有している。家事支援ロボットによって日常生活にも不安はないが、顔を見せると母も喜ぶ。自動走行技術で高速道路は渋滞知らず。帰りは、IT化された農園で消費者の嗜好(しこう)に合わせて栽培された野菜を買って帰るつもりだ。明日は在宅勤務。息子の宿題を見てやろう―。
ソサエティー5・0が実現すれば、こんな未来が現実になるかもしれない。少子高齢化、資源に乏しく脆弱(ぜいじゃく)なエネルギー基盤、都市への一極集中―。ソサエティー5・0は、こうした先進国特有の課題をIoT(モノのインターネット)や人工知能(AI)、ビッグデータ(大量データ)、ロボットといった新技術で解決し、豊かで活力ある未来社会を目指す。
【日独の違い】
1月に閣議決定した政府の「第5期科学技術基本計画」の柱にも位置づけられ、官民挙げて強力に推進する方針が示された。旗振り役のひとり、三井不動産の岩沙弘道会長は「人生の選択肢を広げる試み」と説明する。その世界観を体現する企業でありたいと語る日立製作所の中西宏明会長は「世界に誇る日本発のコンセプト」と表現する。
「ドイツは4・0なのに日本はもう5・0なのか」―。ユーモア交じりに語るのはドイツ産業連盟のウルリッヒ・グリロ会長。もちろん「4・0」「5・0」は技術進歩のスピードを競い合うものでも規格争いでもない。
日独の違いは、新たな技術で何を実現するのかに起因する。IT活用による製造業の高度化を、18世紀の機械化に比肩する「第4」の革新と位置付ける「インダストリー4・0」。これに対し、社会の成り立ちに主眼を置くソサエティー5・0は「狩猟社会」を起点とする進化の過程で「農耕社会」「工業社会」「情報社会」に続く「5番目」の新たな社会を目指す取り組みであることから「5・0」と称する。
【意識改革を】
日本が蓄積してきたエネルギーの効率利用や高品質なインフラ、医療、防災対策―。これらを広く社会に生かし経済成長につなげるうえで欠かせないのが、オープンイノベーションの発想と、企業横断で取り組む「協調領域」を戦略的に定め社会実装を急ぐ姿勢だ。総合科学技術・イノベーション会議議員を務めるトヨタ自動車の内山田竹志会長も「産業界は意識を変え、協調領域をもっと増やさなければならない」と指摘する。
一方で、ビッグデータをめぐる“苦い経験”から新たなビジネスに踏み出すことをちゅうちょする企業もある。それは同時に国が講じるべき施策の必要性を浮き彫りにする。
(2016/8/4 05:00)