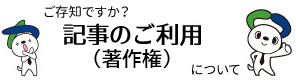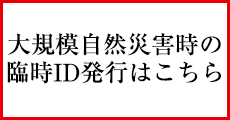[ オピニオン ]
(2018/2/21 05:00)
ドイツが進める第4次産業革命「インダストリー4.0」で重要な役割を果たすのが「デジタルツイン」の概念だろう。実物の製品や生産設備についてそれらに対応するデジタルデータの双子(ツイン)を作り、そのバーチャルモデルを使ってシミュレーションを繰り返す。試作など実世界での作業に移る前に上流で問題を徹底的につぶしておき、無駄を省きつつ作業を効率化するという合理的な考えに基づく。
「バーチャルファーストこそ大事だ」。シーメンスでデジタルファクトリー部門CEOのヤン・ムロジク氏は、米国のトランプ大統領の十八番(おはこ)である「アメリカファースト」にならってか、デジタルツインの手法をモノづくりに積極導入するメリットをこう強調する。
デジタルツインの活用事例として同氏が挙げたのが、金属積層造形(AM)との連携によるモノづくり。特に樹脂部品の量産に使われる射出成形金型はモノによっては数千万円もの製造コストがかかる高価な部材だが、何度も使用しているうちに金型が欠けてしまう場合がある。その壊れた部分をきちんと修繕して元通りの状態で使えるようにするのにも、デジタルツインと金属AMが役立つという。
まず、金型と工作機械のデジタルツインをもとに、壊れた部分を切削加工によって除去して、そこに新たな金属素材をAMで充填、再びマシニングセンターで表面を仕上げる――といった一連のシミュレーションを行う。簡単に言えば、こうしたシミュレーションでの良好な結果をそのまま、実際の工作機械と金属AM装置の側で活用することで、効率的かつ高品質の金型修繕が実現できるというわけなのだ。
もう一つ、デジタルツインと金属ADの特徴を生かせる事例として紹介したのが、拘束条件に従って最適な3次元形状(トポロジー)を生み出すジェネレーティブデザインとの組み合わせ。精製所で使われる高温バーナーシステムでは、従来品の長さが3.4メートルだったのに対し、ジェネレーティブデザインによる設計では半分の1.7メートルと短くなり、部品点数も半分にまで削減できた。
その秘密は生物のように有機的で入り組んだ内部構造にある。こうした複雑な形状だと切削での加工は不可能だが、金属を1層ずつ積み上げて目的の立体を作るAMであれば対応可能。しかも、そうした形状を自動生成するための3DCADまで同社が提供し、パラメーターを変えながら条件に合致するようシミュレーションを重ねた後、初めて金属AMで試作を行う。
「シーメンスは永年、実世界での工場自動化に強みを発揮してきた。以前から製造分野のデジタル化は重要だと認識していたが、仮想世界のモノづくり戦略で主要な基礎となったのが2007年の米UGS(現シーメンスPLMソフトウエア)の買収だ。それ以降、合計約100億ユーロ(約1兆3000億円)を投じて(買収によるソリューションの)ポートフォリオを増やしながら、仮想世界、実世界、デジタルツイン、工場現場を統合し、顧客にとって最善のソリューションを提供するためのアプローチをとっている」(ムロジク氏)
つまり、これまでのような工場の製造現場での自動化にとどまらず、包括的なデジタル戦略のもと、上流の製品設計から製造計画、製造エンジニアリング、製造実行、サービスという顧客企業の全てのバリューチェーンに関わることで、事業領域を飛躍的に広げようというしたたかな狙いがあるのだ。
シミュレーションモデルも製品や製造設備の機械構造にとどまらない。電気回路関係、ソフトウエアまで含めて、デザインとシミュレーションを満足するレベルまで繰り返すことで、実際の製品のプロトタイプを作ったり、製造ラインを作ったりする前に問題点をあぶりだせる。
さらに一連のプロセスのデータは、クラウドベースのオープンIoT基盤「マインドスフィア」で収集・分析され、製品、製造、それぞれのデジタルツインおよび現物でのパフォーマンスをフィードバックしながら、「全体プロセスの連続的な改善につなげていく」(ムロジク氏)のだという。
もちろん、顧客側にも事情がある。製品の市場投入までの期間短縮、特注品に素早く対応できるだけの柔軟性、品質の向上、コスト削減…。こうした課題を解決し、競争に打ち勝つための手立てとして、インダストリー4.0やデジタルファクトリーへの期待はことのほか高い。
デジタルツイン、IoT基盤、そしてAMと、最先端のデジタル手法を重層的に連携させることで新しいモノづくり技術が生み出されてきている。それと同時に、ソリューションプロバイダーと産業ユーザーとの関係もこれまで以上に密接となり、デジタルファクトリーの構成ソフトウエアを握るシーメンスのような企業のプラットフォーマーとしての存在感もより高まっていくだろう。
意地の悪い見方をすれば、プロバイダーがユーザー企業のモノづくりの根幹にまで入り込み、そこから持続的に収益を上げる構造で、ユーザーとしては生殺与奪を握られると言っても過言ではない。どのプラットフォーマーと組むかで、ゆくゆくはビジネスの成否が分かれるような事態が出てくるかもしれない。
(デジタル編集部・藤元正)
(2018/2/21 05:00)