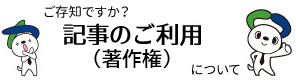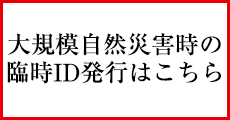(2021/4/20 12:00)
―今後の可能性を探る―
Markstone知的財産事務所 代表弁理士 中村 祥二
特許権ばかりが知的財産権ではない。意匠権と商標権は、最近の法改正により保護対象が拡充され、企業からの注目も増している。ただ、両者の保護対象が重複する場面ではどのように取り扱うべきなのか、一見すると分かりづらい。企業活動を支援するツールとしてどのように意匠権・商標権を使い分ければよいのか。両者の相違点とともに紹介する。
■意匠権とは―デザインの対象拡充
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などの知的財産権は企業活動を自社に有利に進めるためのツールとして活用されている。これまでは特許権を中心に語られることが多かったが、最近では、意匠権・商標権も存在感を増してきている。
意匠とは、平たく言えばデザインのことだ。意匠権は創作されたデザインを独占する権利で、企業が独自に生み出したデザインを他社の模倣から守る役割がある。
意匠権を取得するには、特許庁に所定の様式で出願手続きを行う必要があり、その審査では、新規性(世の中にすでにあるデザインではないか)や創作非容易性(世の中にあるデザインから容易に創作できなかったか)などが審査される。審査に通過すれば、最長で出願から25年間、デザインの独占権を得ることができる。
従来、意匠権で保護できるデザインは「物のデザイン」に限られていたが、昨年、保護対象が拡充され、画像や建築物、内装のデザインも保護できるようになった(図1)。その背景には「デザイン経営」という考え方がある。
「デザイン経営」とは、デザインを企業価値向上のための経営資源として活用し、ブランド力とイノベーション力を向上させる経営手法だ。すべてのモノがネットワークにつながり、消費スタイルがモノからコトに変化した今日では、ユーザーインターフェース(UI)やユーザーエクスペリエンス(UX)が消費者の購買行動に果たす役割が増しており、デザイン経営は事業活動における必須の考え方となっている。
一方、従来の意匠法は「物のデザイン」を権利の対象にしており、デザイン経営を進める上でのUIやUXを十分に保護できていなかった。
そこで、デザイン経営の実践を後押しするべく、画像や建築物、内装のデザインについても保護できる意匠制度に整えたのが昨年施行された改正意匠法だ。
■商標権とは―企業ブランドを守る
商標は自社の商品やサービスと他社の商品やサービスとを区別するための目印をいう。商標権は自社商品・サービスを示す目印を独占的に使用できる権利で、商標を通じて認識される企業のブランドを守る役割がある。
商標権を取得する場合は意匠権と同じように、特許庁に出願手続きを行う必要があり、審査では他社の商品・サービスと区別するための目印として機能するかどうかや、他社がすでに取得した商標権と紛らわしくないかなどが審査される。
権利期間は10年だが、存続期間の更新が可能で、権利者が望めば半永久的に権利を維持できる。商標権の対象は文字、図形、記号、立体的形状、色彩、音、動き、ホログラム、位置の商標である(表1)。
ここで注意が必要なのは、商標権は自社商品・サービスを示す目印の使用を独占する権利だが、“目印"の使用を際限なく独占するための権利ではないことだ。使用を独占できる範囲は、商標出願の際に指定した商品やサービスの範囲内に限られる。
例えば、「ASAHI」という文字でも、飲料の分野ではアサヒグループホールディングスが商標権を保有し、靴の分野ではアサヒシューズが保有している。商品やサービスの範囲の相違によって、消費者が間違えることはないから、同一または類似の商標でも併存できることになっている。
商品・サービスのブランド力を高めることで価格競争に巻き込まれない販売戦略を描けることもあり、今日では商標権の重要性も広く認識されている。
保護対象の重複と相違点
このような意匠権と商標権について、通常は、製品デザインについては意匠権を取得し、文字や図形など企業の商品・サービスを示す目印は商標権を取得するのが一般的だ。しかし、最近の法改正や規則の改正により、保護対象が重複する場面が増えてきている。
具体的には、意匠権、商標権のいずれでも、立体的な形状や、スマホアプリのアイコン画像、店舗の外観や内装が保護されうる。このような保護対象が重複する場面では、半永久的に権利を維持できる商標権を取得したほうがよさそうにも思えるが、そう簡単に決めることはできない。
理由は、審査内容の違いだ。
前述のとおり、商標権の審査では、他社の商品・サービスと区別する目印になりえるか審査される。そして、立体的な形状や店舗の外観・内装は、他社の商品・サービスと区別する目印となりうる文字や図形などの要素がなければ、通常は審査を通過しない。例外として、長年の使用によって有名になった場合に限って権利が認められる。
一方で、意匠権の審査では、文字や図形などの要素がなくても、デザイン自体が新しく、すでに存在するデザインから容易に思いつかないものであれば権利を取得できる。意匠権と商標権とで保護対象が重複しても、実際に権利を取得できるかどうかは別問題なのだ。
使い分けをいかに判断するか
そうすると、どのように使い分けるかは、権利取得したいデザインや目印の置かれた状況によって個別に判断していくほかないだろう。ただ、意匠権・商標権の目的に応じた考え方はある(表2)。
画像に関しては、デスクトップ画面や操作画像などのUI/UXに関わる画像デザインについては、意匠権での保護が向いている。ただ、そのようなデザインが画像全体として他社の商品・サービスと区別するための目印として機能するなら商標で保護することも検討すべきである。一方で、アプリのアイコンについては、他のアプリと区別するために使用されるため、商標での保護が向いている。
次に、建築物や内装に関しては、基本的には意匠権での保護が向いているだろう。前述のとおり、商標権は他社の商品・サービスと区別する目印となりうる文字や図形などの要素がない限り、容易には審査を通過しないためだ。ただ、長年の使用によって、特定の建築物や内装を見ただけで「あの店だ」と理解できるような状況になっていれば、商標権による保護を目指すべきである。
なお、意匠権での保護が有利と考えられる場合でも、意匠権を取得するには、新規性などの要件を備えていなければならない点には注意が必要だ。自らデザインを公開した状況でも原則として意匠権を取得できない。
特に建築物や内装のデザインについては、多くの人が目にすることができる場所に作られることが一般的で、作ったとたんに第三者に知られてしまう可能性が高い。そうなると、意匠権でのデザインの独占は難しくなる。
今後の方向性
このように、意匠権と商標権とでは、権利の目的や権利取得の要件が異なり、保護対象が重複する場面でも状況に応じて使い分けをする必要がある。
ここで、最近では車のフロントグリルのように、製品やサービスに使われるデザインが他社の商品・サービスと区別する目印としても認識される場面が増えている。商品やサービスに施される統一感あるデザイン(意匠)が商標としても機能するのだ。
そのようなデザインの活用場面を見据え、意匠権の保護範囲を商標権で引き継ぎ、長期にわたるデザイン保護を可能にする手法は、両者の保護対象が広がった今日では検討に値する。
一例として、ニコンの一眼レフカメラのグリップ部分の赤い線が挙げられる。意匠権を取得していたデザインについて、位置商標という形で半永久的な商標権を取得したものだ(図2)。カメラ好きの人にとっては、グリップ部分の赤い線を見れば「ニコンの」とわかるデザインになっている。
(2021/4/20 12:00)