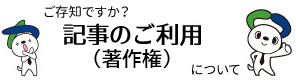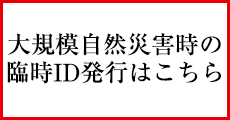- トップ
- 科学技術・大学ニュース
- 記事詳細
[ 科学技術・大学 ]
(2016/11/2 05:00)
理化学研究所などは、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を使って、統合失調症や脊髄小脳変性症といった精神・神経疾患の病態を解析した研究成果を相次ぎ報告した。統合失調症では神経細胞の分化段階の異常を発見。脊髄小脳変性症では、神経細胞でカルシウムイオンの搬入経路を構成するたんぱく質の一部分が異常に蓄積する病態を再現した。発症機構の解明や創薬への貢献が期待される。
理研脳科学総合研究センターと慶応義塾大学、順天堂大学などの研究グループは、染色体異常症の一つ「22q11・2欠失症候群」が統合失調症の発症率を上昇させる点に着目。同症候群を持つ統合失調症患者と健常者からiPS細胞を作り、神経細胞に分化する過程を調べた。
その結果、神経細胞に分化する前段階の細胞塊「ニューロスフィア」の直径が、患者は健常者に比べて約30%小さかった。また細胞塊から分化した細胞のうち、神経細胞の比率が健常者は約90%だったのに対し、患者は約80%にとどまった。
この欠失症候群を持たない統合失調症患者の死後脳の解析でも、神経細胞とそれ以外の細胞の比率の異常を確認。分化効率の変化が統合失調症の病因に関わっている可能性を示した。
一方、理研多細胞システム形成研究センターと広島大学、京都大学の研究グループは、運動機能に障害が出る脊髄小脳変性症6型(SCA6)の患者からiPS細胞を作製。このiPS細胞を小脳の神経細胞の一つ「プルキンエ細胞」に分化させ、病態の一部を再現した。
患者由来のプルキンエ細胞は形態が脆弱(ぜいじゃく)であることが判明。既存薬である甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンや、筋萎縮性側索硬化症(ALS)治療薬「リルゾール」に、この脆弱性を抑える効果があることも分かった。
二つの研究成果は2日、英国と米国の科学誌の電子版にそれぞれ掲載される。
(2016/11/2 05:00)