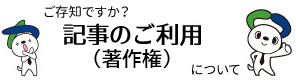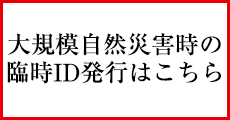(2020/1/13 05:00)
失われた20年、あるいは30年と言われた平成の時代。民生電機・電子分野を中心に韓国や中国の企業が世界市場で躍進し、「モノづくり大国・ニッポン」の地位が危うくなってきたのではとの見方もある。方や米IT大手も自動運転などの分野で着々と足場を固めている。モノづくりをめぐる状況が急速に変化する中、日本の企業はどこを目指せばいいのか。モノづくり日本会議が2019年9月に都内で開催した「第1回モノづくり力徹底強化検討会」での東京大学大学院経済学研究科の藤本隆宏教授(東京大学ものづくり経営研究センター長)の講演内容から、日本の製造業の勝ち筋を考えてみたい。
自社標準品、売り切る戦略を
東京大学大学院 経済学研究科教授・東京大学ものづくり経営研究センター長 藤本隆宏氏
冷戦終結後の平成の約30年間、一部のマスコミなどは「日本の製造業は駄目になった」「サービス化の時代には脱製造業だ」というような報道を繰り返してきた。しかし、それらは基本的な統計データも、現場の生産性向上の実態も、経済理論も原則も分かっていない粗雑な議論だった。こうした根拠の無い気分的な悲観論は何も生まない空論である。
確かに日本のGDP(国内総生産)はこの30年間、500兆円前後で停滞した。また、90年の日本のGDPに占める製造業の割合は25%強だったのが、2000年代には20%前後に低下した。しかしその後はこの水準を維持し、17年には22%、約110兆円。ちなみに米国の製造業のGDP比率は10%強。G7(先進7カ国)で製造業がGDPの20%以上を占めるのはドイツと日本だけだ。日本の製造業は、成長はしなかったが衰退もしなかった。勝ったというにはほど遠いが、負けてはいない。個別に見れば元気の良い産業や企業もある。こうした単純な事実を、製造業衰退論は見落としている。
経営者は潮目を読め
この30年間、日本の製造業の企業数は約半分に減り、就業者数も3分の2の約1000万人に減った。とはいえ付加価値総額はあまり減っていない。これは一社当たりの付加価値が約2倍、付加価値生産性は約1・5倍の一人当たり1100万円人になったことを意味する。仮に非製造業を含む日本の全就業者が製造業並みの生産性を出せれば、日本のGDPは700兆円を超える。これが、30年のグローバル産業戦争を生き抜いた日本製造業の実力である。
さらに物的生産性(物量単位の生産性)であれば、日本にはまだまだ世界一の分野がある。自動車もそうで、我々の現地調査によれば、日本の組立工場の人・時当たり台数は、日本企業の中国現地工場の約2倍、中国現地企業の3倍以上と推定される。実は造船業もそうである。
米国の調査では、ある九州の中手造船所の生産性が世界最高で、中国企業平均の5倍程度と推定される。他方、中国の溶接工の賃金は日本の3分の1程度と言われる。国際経済学の比較優位理論を適用するまでもなく、物的生産性が5倍で賃金が中国の3倍であれば、単位コストでは日本の勝ちとなる。実際、コモディティーの貨物船を作りながらトヨタの2倍以上の利益率を出してきた中手造船所もある。
現在は船価低迷で日中韓ともに造船は赤字基調だが、一部の中手企業は、造船不況の中で設備増強に出ている。世界造船不況の今、自社が受注残を確保していれば、当然シェアは上がる。次の増産期にそのシェアを維持できれば、会社は成長する。中手企業の中には、このように潮目を読み切る優れた経営者が存在する。電子部品や産業機器などの他業種でも、優れた戦略を立てる企業や経営者が近年は増えてきたと感じている。製造業衰退論者は流行語に盲従(もうじゅう)せず、こうした個別産業の実態や背後にある経済論理を見ておくべきである。

サイバーフィジカルの主導権カギに

コテコテのモノづくりで多数の1兆円企業
今のデジタル化の時代、日本にはGAFA(グーグル、アップル、フェイスブック、アマゾン)のようなプラットフォーマーは残念ながら1社も出てきていない。
しかし、こうしたプラットフォーマーに「上空」(ICT層)の制空権を握られながらも「地上」で良く戦い、成果を出している日本企業は、探せば少なくない。そうした身近なところから学ぶのが先決だろう。
これら優良製造企業は、デジタル化の時代であっても「コテコテのモノづくり」を愚直に続けている。「デジタル化の時代に『モノづくり』は時代遅れ」といった論調もあるが、「強みを伸ばし弱みを補う」という戦略論の基本を踏み外している。
むしろデジタル化時代だからこそ、まねされない「コテコテのモノづくり」の戦略的重要性は増す。設計の比較優位論によるなら、モジュラー型のハイテク・デジタル製品の覇権を争う米中技術摩擦が長く続けば、米国も中国も、面倒な擦り合わせ型の製品・部品・設備は日本などに任せ、得意なモジュラー型に集中する可能性が高い。ここに日本の商機がある。
ただ、コテコテのモノづくりだけをやっていても浮かばれない。そこで出てくるのが設計に関する競争戦略、特にアーキテクチャーの戦略である。例えば標準化戦略もその一つ。一部の欧州企業は「品質にうるさい客」に標準品を売り切る商売が実にうまい。一方、日本企業は、客先のカスタム要求に過剰に応じてコストアップする傾向がある。カスタム品でいじめられてきているので、確かに現場のモノづくり力は高いが、会社はなかなか利益が出ない。
顧客のカスタム要求の中には、とりあえず言ってみただけの項目も混入している可能性がある。これに対し、真のカスタム要求を見切り、そこに集中し、コアの標準設計モジュールと周辺の特殊設計部分の組み合わせで対応することで成功している日本企業も存在する。
日本は一時期「電子立国」を標榜(ひょうぼう)していたが、結果的にはデジタル化した産業の多くが衰退した。「日本はハイテクなら勝てる」という技術至上主義は幻想であった。勝てるか勝てないかを見分ける上で、より重要な概念は「アーキテクチャー」、つまり設計形式だった。
どんなハイテク製品でも、ハイテク設備やハイテク部品の寄せ集めでできるタイプのモジュラー型のデジタル製品では、日本企業は勝てなくなった。しかし、高機能モジュラー製品のための生産設備や部品自体は、調整を必要とする複雑なインテグラル(擦り合わせ)設計として残り、そこでは日本の企業や現場は勝つことができた。組み立ては海外工場でやるとしても、そうしたコア部分は国内で作る。こうした階層別にメリハリの利いたアーキテクチャー戦略が必要である。
このように、一方で「コテコテのモノづくり」を続けながら、他方で、中インテグラル・外モジュラー、あるいは中モジュラー・外インテグラルの「アーキテクチャー位置取り戦略」を明確に選択している企業に、例えばシマノ、村田製作所、キーエンス、ダイキンなどがある。その結果としてグローバル・トップのシェアを獲得しているところは、実際に多くが20%以上の営業利益率を出している。「デジタル化時代のモノづくり企業」のお手本は、身近な日本企業の中にある。単純にGAFAのまねをしようと言うのは現実的ではない。
オープン・プラットフォームの超巨大化というGAFAの「上空」戦略を「恐竜」に例えるなら、「地上」に残る日本企業の戦略は、カスタム化で繋(つな)がれてしまうのではなく、小さいながらコテコテのモノづくりと自社標準の合わせ技で「上空」と繋がる「しぶとい哺(ほ)乳類戦略」である。自動車のような巨大比較優位産業に加えて、数千億―1兆円規模の「強い補完財産業」を多数持つことができれば、わが国製造業は日本経済の再成長を下支えできよう。
ライバル同士「低空」で連携も
インターネット、AI、クラウドコンピューティングなど、いわゆる重さのない世界である「上空」の制空権をシリコンバレーなどに握られている中で、これまで見てきたように、「地上」に残る日本の物財企業は「哺乳類戦略」で戦う。さらにもう一つ大事なのは、「低空」の競争に勝つことである。
重さのある「地上」の世界は、サステナビリティーが問題になるほど困難性が増し、自動車も工場も設計や制御が極端に複雑化しつつある。上空の「計算能力」がいかに巨大でも、それらを直接制御するのは難しい。
そこで上空と地上の中間にもう一つ「低空」(サイバーフィジカル)層を作り、エッジコンピューティング、サイバーフィジカルモデルなどで高速・高精度の制御をしようとの考え方が10年代に広がった。インダストリー4・0や産業用IoT(モノのインターネット)もこの「低空」領域の取り組みである。
従って地上の日本企業は、上空と直接的に繋がる「哺乳類戦略」に加えて、この低空層で主導権を握る必要がある。「低空の戦い」では、上空のグローバルなネットワーク力と、地上のモノや流れに対する深いローカル知識、この二つのバランスが重要である。
米国のGEは前者の力を過信してつまずいたが、ドイツのシーメンスはデジタルモノづくりでこのバランスをうまく取り成功した。
日本には、個別には世界的に強いFA機器や工作機械の企業がいくつもあるが、サイバーフィジカルモデルへの連結など、低空層での標準獲得が進んでいない。海外勢に対抗するためには、かつての薩長同盟のように国内ライバル企業同士での連携が必要になろう。
つまり、上空のGAFAの世界は、米国、中国、インドなど人口大国が中心になる中で、中規模国である日本の製造業は、地上での優位を維持しつつ、いかに上空とつながるか、そしていかに低空戦で負けないかに、当面は専念した方が良いだろう。
(2020/1/13 05:00)