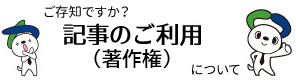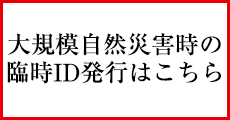(2020/9/24 05:00)
22日付の紙面でお届けした「富岳」をはじめとするスーパーコンピューターの進展とともに、大いに注目されるのが量子コンピューターです。もはや夢物語ではなく、実際に開発されたマシンにより産業分野での応用研究が着々と進められています。モノづくり日本会議では8月25日にモノづくり力徹底強化検討会として「量子コンピューターが拓(ひら)く新世界」と題したウェブ講演会を実施し、日本IBM執行役員最高技術責任者(CTO)の森本典繁氏に汎用量子コンピューターの現在と未来について話していただきました。
桁違いの計算パワー、30年後に性能10億倍へ
日本IBM 執行役員 最高技術責任者(CTO) 森本典繁氏
現在、我々は100ナノメートル(ナノは10億分の1)程度の大きさの新型コロナウイルスに翻弄され続けている。ホワイトハウス科学技術政策局、米国エネルギー省、およびIBMが主導するCOVID―19ハイパフォーマンス・コンピューティング・コンソーシアムでは、スパコンを活用してDNAや遺伝子、分子の解析を行い、ワクチンや治療薬候補を早期に開発しようという研究も数多く進められている。量子コンピューターの話に入る前に、今後こういった桁違いの計算パワーが必要になる背景をまず話したい。
「計算力不足」補う
人工知能(AI)が世界中で爆発的に普及し、コミュニケーションから産業用ロボット、機械、自動運転、医療、株式、金融、法律など幅広い分野に使わるようになった。ただ、現在はまだ狭い分野に適用される「ナローAI」がほとんど。ナローAIは特定の問題を解くことしかできず、学習には大量の正解付きのデータを必要とする。一方でIBMは不完全なデータからでも複合的で多面的な判断ができる「ブロードAI」の実現を目指している。AIだけでなく、IoT(モノのインターネット)や5G(第5世代通信)でのデータ量も、ハードウエアの成長に比べはるかに速いスピードで増えている。
このように遺伝子や分子の解析、AIの必要性が増したことから生じる、コンピューターリソースに対する需要の爆発的な増加は、現在世界中の半導体メーカーが開発して発展させられるハードウエアの成長よりも格段に速い。やがてコンピューターリソースが世界中で不足するということが以前から予想されている。そのギャップを埋めるための重要な技術の一つとして量子コンピューターが位置付けられている。
現在の我々が使っているコンピューターはビットという単位で動作し、決定的に1または0で状態を表現する。2ビットであれば4通り表せるが、こうした古典ビットでは一度に一つの場合しか表現できない。それに対し、量子コンピューターが情報を格納する量子ビットは、1と0を共存させ同時に1と0を表現できる。つまり2量子ビットで4通り、3量子ビットで8通り、10量子ビットであれば1024通りの場合を同時に表現できる。たった10量子ビットで今のビットの1024倍、20量子ビットで100万倍、30量子ビットあれば10億倍通りものスケール(規模)を獲得できることになる。
このように、少ない量子ビットで指数関数的に大量の場合を表現できることに加え、一度の処理で全ての場合に対して演算を適用できる。そのため、例えば全ての場合について総なめにして計算するようなパターンを1回で済ませることができる。非常にたくさんの場合の数を同時に計算する能力が、これまでのコンピューターとの大きな違いとなる。
高級言語も
二つ目の違いは、こうして表現された量子ビットを互いに演算する種類が多岐にわたる点。量子重ね合わせ、量子干渉、量子もつれといったさまざまな量子効果を駆使することで単純な古典回路に加え、非常にバラエティーに富んだ多くの演算ができるようになる。
だからといって使い勝手が良くないかというと、そんなことはない。我々が開発する汎用量子コンピューターではユーザーは通常のソフトウエアを使い、高級言語のPythonやJavaでのプログラミングが行える。現在のコンピューターサイエンスのエンジニアであれば、それほど違和感なく入っていけるというのが非常に重要なポイントとなる。
実際の処理ではプログラムが量子アルゴリズムを呼び出した後、量子効果を利用した演算子を対応するマイクロ波に変換し、マイクロ波を用いて逐次物理的に量子ビットを操作することにより、量子アルゴリズム全体を実行する。演算結果として量子ビットから読み取られた微弱な信号は増幅されながら戻されていき、最終的に(現行の)古典コンピューターで読めるデータに変換される。
ちなみに量子ビットが格納される筒は、一番冷たいところで15ミリK(Kは絶対温度)に保持される(摂氏では約マイナス273度C)。ここまで冷却が必要なのは、超電導状態での動作を維持するということと、非常に微細な信号を操作するので周囲のバックグラウンドノイズを少なくするためだ。絶対零度よりもほんの少しだけ温かいという温度を安定して保持するためには、非常に精妙な温度操作が必要となり、高度な技術が求められる。
産学連携でコンソーシアム
「量子ボリューム」
次は量子コンピューターの性能向上について。実は単純に量子ビットの数が多ければいいというものでもない。それぞれの量子ビットについて重要なことは、ノイズを減らすことと、安定した量子状態を長時間保つこと。量子状態というのは、あたかも空中で回転するコインのように回転している間だけ量子状態を発揮し、その間だけ演算を行える。つまり、全体の性能を上げるにはビット数を増やすことも重要だが、量子状態を維持する時間を延ばすこと、さらに各量子ビットのノイズを減らすという三つの要素が必要。そのためIBMでは、「量子ボリューム」という総合的な性能指標を使って量子コンピューターの性能を評価している。
2017年以降の量子ボリュームの性能の進歩は表に示した通り。過去4年間で実は毎年2倍ずつ総合演算指標を上げてきている。17年が2、その次の年以降が4、8、16、32というように、量子ボリュームが確実に上がっている。実は8月初めに量子ボリューム64達成のアナウンスがあった。もっとも重要なのは、今後10年近くにわたるこの先のロードマップを示していること。何年後くらいに画期的なアプリケーションが動作するのか、大体予測できるためだ。
IBMでは20台以上の量子コンピューターを常時稼働させ、クラウド経由で世界中のパートナーの皆様に提供している。その稼働率は97%を超える。そのうちの一部は「IBM Qエクスペリエンス」という形で世界中の研究者、学生の皆様に無償提供している。これらで合計2000億回近くの演算がなされ、そこから出てきた科学技術論文は250本超。さらにもっともハイエンドの量子コンピューターにアクセスできる「IBM Qネットワーク」にアクセスできるメンバー、企業、大学などの団体も、8月時点で115を超えている。
日本に実機設置
日本では18年に慶応義塾大学とともに、世界に先駆けて産学連携の研究拠点を矢上キャンパス(横浜市港北区)に立ち上げた。当初はみずほフィナンシャルグループ、三菱UFJ銀行、三菱ケミカル、JSRが参画し、初め10人以下だった研究チームも30人近くまで規模が拡大している。
さらにIBMは慶応義塾大学に加え、東京大学との研究パートナーシップ締結について昨年12月に発表した。目玉が三つあり、まず門外不出の量子コンピューターの実機を日本に設置すること。ドイツのフラウンホーファー研究機構とドイツIBM、東京大学に米国以外で初めて、IBMの量子コンピューター「IBM Q System One」が来年設置される。
二つめは東京大学へのハードウエアの開発センターの開設。三つめが産学連携の研究センターにとどまらず、それを発展させた産学連携のコンソーシアムづくり。東京大学が創設する「量子イノベーションイニシアティブ協議会」に、慶応義塾大学、東芝、日立製作所、みずほフィナンシャルグループ、三菱UFJフィナンシャル・グループ、JSR、DIC、トヨタ自動車、三菱ケミカル、JSR、日本IBMが加わると7月末に発表した。
一方で、IBMは量子ネイティブ世代の育成にも力を入れている。19年に山梨県で開催したキャンプでは、アジア中心に世界14カ国から120人以上の若者が集まった。つい最近では量子コンピューターについてリモートでのサマースクールも実施している。
先ほど量子コンピューターの性能指標で、30年後には今の10億倍ぐらいの性能になるとの予想を示した。量子ネイティブ世代が私のような年になったころの世界には、今とは全く違う技術、違う価値が生まれてきているのではと大いに期待している。
(2020/9/24 05:00)