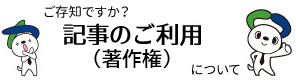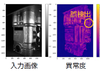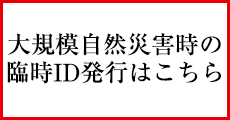[ ICT ]
(2017/10/1 12:00)
米インテルは、人工知能(AI)向けに脳の仕組みを真似た自己学習チップを開発したと25日に発表した。学習と推論の機能を1チップに搭載し、処理が高速に行える上、通常のCPUやGPUに比べて低消費電力なのも特徴。クラウドとやりとりせずに機械学習の処理が単体で行えるため、周囲の環境に対しリアルタイムかつ自律的に対応できる。自動車や産業用途、ロボットなどへの応用が想定されるとしている。
コードネーム「Loihi(ロイヒ)」と名付けられたこの試験チップは、脳の仕組みを模した「ニューロモーフィック・チップ」の一種。13万のニューロン(神経細胞)とそれらが接合する1億3900万のシナプスを、14ナノメートルのプロセス技術を使ってメニーコアのハードウエア上に再現した。2018年前半に、AIの先端研究を行う大学や研究機関向けに提供される。ちなみに人間の脳は約1000億のニューロンで構成されると言われている。
深層学習に代表される機械学習は大きな進展を遂げているが、AIに物事を認識させるには大量のデータが必要。それに対し、ニューロモーフィック・チップは周囲から取り込んだデータをもとに学習しながら賢くなっていく。次世代の機械学習手法である「教師なし学習」や「強化学習」にも応用できるという。
研究部門インテル・ラブズの社長を兼務するマイケル・メイベリー副社長は、ニュースリリースの中で、こうした自己学習チップの端末(エッジ)側での活用について、カメラで捉えた映像から、道路の交通量を自動認識し、なるべく渋滞が起きないよう赤信号のタイミングを調整したり、人がさらわれるのを自動で報告したりといった事例を挙げた。
そのほかにも、個人の心臓の心拍数を常時モニターし、その変化から異常を発見したり、サイバーセキュリティー関連ではシステムの平常状態を学んだのち、システム侵入やハッキングをいち早く検知したりするのにも役立つとしている。
【ニューロモーフィック・コンピューティングについての動画(Credit: Intel Corporation)】
(2017/10/1 12:00)