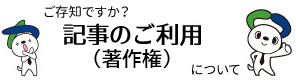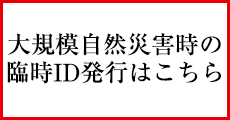(2020/4/28 05:00)
4月18日は「発明の日」。1885年4月18日に現行特許法の前身である「専売特許条例」が公布されたことに由来する。特許や意匠、商標など、産業財産権の普及・啓発を目的に制定された。日本の産業競争力を高めるためにも、知的財産の創出や保護、活用のあり方について、あらためて考えたい。
スタートアップ支援拡大
政府は次世代産業の担い手を確保するため、スタートアップ企業の支援策を拡充している。2020年度からは、スタートアップ企業に出資した企業の税負担を軽減する「オープンイノベーション促進税制」が始まり、資金面の支援が整った。一方、イノベーション創出の分野では、特許審査期間の大幅短縮などを通じて知的財産権の活用を喚起している。日本の産業競争力を飛躍させるためには、特に知財に関する政策が欠かせない。
日本は国家間のイノベーション競争で劣勢に立たされつつある。スタートアップ投資に関しては、米国では18年度に約14兆円、中国では約3兆5000億円の投資が実行されたのに対し、日本は約2800億円にとどまった。開業率についても、米国や英国が10%前後で推移する一方、日本はその半分の5%だ。すでに海外では自動運転などで成果を上げており、日本の産業競争力は相対的に低下しつつある。
長らく日本では、中長期の成長力を示す潜在成長率が1%程度で頭打ちの状態が続いている。日本経済に漂う閉塞(へいそく)感を打ち破るには民間主導の活力を引き出すしかない。他方、日本企業が保有する現預金は18年度に過去最高の240兆円に達しており、滞留する資金を有効に活用できていないとの指摘が上がる。政府関係者は「内部留保が将来の(日本の)屋台骨につながっているのか、という問題意識がある」と説明する。
こうした状況を踏まえ、政府は税制改正や知財政策などを通じてスタートアップ支援を積極化している。この4月には、オープンイノベーション促進税制を創設。企業が一定額以上の投資をした場合に出資額の25%を課税所得から控除する措置で、企業の内部留保をスタートアップなどへの投資に回す。「各国に比べて日本のスタートアップ投資は少ない」(経済産業省幹部)とされ、20年度税制改正の目玉にする。
審査期間を大幅短縮
一方、知財関連の政策では特許庁が幅広い支援メニューを用意している。有望なスタートアップについては、専門家が知財の相談に応じる事業「知財アクセラレーションプログラム(IPAS)」に取り組んでいる。弁理士やコンサルタントら専門家が技術を権利化すべきかどうかを助言したり、特許出願などをサポートしたりする。18年度は再生医療や量子コンピューターなどを持つ10社を、19年度は先端技術を持つ15社を選定した。
このほか18年7月からは、通常の審査より短い期間で特許を取得できる「スーパー早期審査」と「面接活用早期審査」の二つの仕組みを運用している。一つ目のスーパー早期審査は一次審査から最終処分までの期間を大幅に短縮し、平均で約2.5カ月の取得を可能にした。期間が短いため、企業側の業務負担が少なくなる利点もある。スタートアップ対応のスーパー早期審査の申請件数は、19年12月末までに累計約350件に達した。
面接活用早期審査は一次審査の前に担当審査官と面接でき、平均約5カ月で取得できる。技術の意義など書面に書きにくい内容を説明したり、審査官から特許性の助言などを受けたりすることが可能だ。スタートアップ対応の面接活用早期審査の申請件数は、19年12月末に累計約40件となった。
19年度からは権利の取得に必要な料金や手続きも減免し、利用を喚起している。スタートアップに関しては審査請求料・特許料や国際出願の手数料を通常の3分の1程度に引き下げている。また企業規模を示す証明書類の提出も不要にしており「煩わしい提出作業をなくし、口頭で説明すれば良いことにした」(特許庁)。19年4―12月の審査請求料の減免申請件数は約1500件、特許料の減免申請件数は約300件となった。
スタートアップの成長は不確実性が高く、財務に余力がなければ手を出しにくい。ただ世界的にコーポレートベンチャーキャピタル(CVC)の動きが拡大する中で、日本企業が手控えれば米国や中国との差が広がるばかりだ。成長のけん引役を担うスタートアップを輩出し続ける必要がある。
インタビュー/経済産業省 特許庁長官 松永明氏「出願人の立場で正しく理解」
2019年に旭化成の吉野彰名誉フェローがノーベル化学賞を受賞したが、その発明の証拠となったのは論文ではなく特許という公的文書だった。産業界の研究者にも明るい話題となり、あらためて特許の役割が重要視される契機となった。今後、日本が成長を続けるには、特許などの知的財産制度を一段と広めていく必要がある。特許庁の松永明長官に現況や今後の展望を聞いた。
□ □
―吉野名誉フェローの成果をどう見ていますか。
「知財制度の目的は発明を奨励し、産業の発達に寄与するということ。吉野名誉フェローのリチウムイオン電池の発明はその意義通りであり、知財制度の原点に立ち止まって考える良い機会になった。また産業界の研究者を励ますことになった。我々もノーベル賞を受賞するような研究を審査しているということを認識し(それに対応できるよう)審査能力を維持しなければいけない」
―審査能力を高めるための取り組みについて教えてください。
「日本は特許権利化の期間で世界最高水準を達成したが、早いだけではなく審査の質も高くないといけない。出願人の立場に立ち、発明したものを正しく理解し、権利範囲について適正なものにすることが重要だ。権利範囲が狭ければ先行事例と比較して権利を認めやすいが、特許の範囲が“細い"ものになる。そうではなく、出願人が考えていることをどう権利の中で認めていくかが質の高さとして求められる。より丁寧にコミュニケーションを行う」
―先端技術への対応策は。
「日本は世界に先駆けて人工知能(AI)関連とIoT(モノのインターネット)関連の特許審査基準に関する事例集を発表している。日本の判断基準を示すことで、世界全体で審査のハーモナイゼーション(制度調和)を促している。日本の審査基準が世界に通じることになるので、日本の企業にとってもプラスだ」
―審査能力はどのように強化していますか。
「AIに関して深い知識を持った人が、機械や化学など他分野のチームと連携し審査している。一般的にはAIを組み込んだ技術という形で出願されており、例えば機械関連の審査官とAIの専門家との連携が非常に重要になる。横連携をしながら常に全体の底上げを図っており、欧米など主要な特許庁と比べて早い取り組みと自負している」
(2020/4/28 05:00)