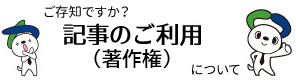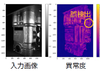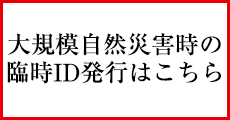- トップ
- 科学技術・大学ニュース
- 記事詳細
[ 科学技術・大学 ]
(2016/11/24 05:00)
金属の周りに、配位子(中心原子に結合する化合物)が取り巻く低分子の錯体を研究する「錯体化学」は、化学の伝統的な分野の一つ。これに対し、配位子がジャングルジムのように立体的につながる「多孔性配位高分子(PCP)」を開拓してきたのが、京都大学大学院工学系研究科の北川進教授だ。メタンや水素のガス分子を、混合ガスから分離・濃縮・貯蔵する応用に期待が集まる。最近では狙った分子の大きさに合わせ、穴が縮小・拡大する“賢い材料”に展開が進んでいる。
(編集委員・山本佳世子)
【柔らかな有機材】
PCPは金属有機構造体(MOF)とも呼ばれ、錯体化学の研究が土台だ。錯体は、有機溶媒に溶かした溶液状態で、触媒や磁性材料としての機能に注目することが多い。しかし、この錯体が3次元につながってできたPCPは、多孔質材料としてまったく異なる使い方となる。
ナノサイズ(ナノは10億分の1)の穴が多数ある上、穴のでこぼこによって材料表面の面積が格段に広い。穴の大きさに合わせてガス分子などさまざまなものを吸着し、分離したり濃縮したりする使い方だ。
同様のものとしてゼオライトと活性炭が古くから使われている。これらは無機材料で安定しているが、望ましい大きさの穴だけを規則的に作り、特定分子だけをより分ける高機能材料にするといった工夫がしにくい。
これに対してPCPは柔らかな有機材料であり、穴の設計が自由だ。合成も200度C以下で、中心に入る金属イオンと配位の有機物を混合するだけと簡単なのも魅力だ。
【大ガスと研究】
PCPの考え方が出てきたのは1990年ごろとなる。しかし、有機材料であるため、弱くて不安定だった。北川教授は東京都立大学(現首都大学東京)在籍の97年に、ネットワーク構造を維持し、その空間を活用した酸素とメタンの交換に成功、最初の論文を発表した。2000年にかけて改善に成功し、安定した材料として提供できるようになった。
最初の発表に向けて力となったのが、近畿大学に在籍中の90年から始めた大阪ガスとの共同研究だ。北川教授の学会発表で、気体吸着の機能に関心を持った同社が声をかけた。大学の錯体研究室と異なり、ガス会社だけにガスの分析装置がそろう。北川教授は、PCPの安定性をガス分子の出入りで証明できると踏んだ。合成したPCPを都立大から送り、同社が測定することを繰り返し、成功につながった。
PCPは少量のガスに対してはセンサー材料として、多量のガスに対しては取り除いたり貯蔵したりする材料として活用が可能。排ガスの中でも毒性の高い一酸化炭素(CO)や、温室効果ガスでもある二酸化炭素がターゲットだった。
さらに近年、北川教授は有機の多様性を生かしてガス分子の分離を促す仕組みを導入した。例えば層状のPCPが2枚、並行に重なってスライドしたり、相互にくぼんで組み込まれたまま動いたりする。すると穴の大きさが変わったり、空間がなくなったりする。
つまり、目的の分子が入ってきた場合、その大きさに合わせてきゅっと穴が縮んでとらえ込み、その後で穴を広げて放出するといった操作が可能になる。
《分子の穴 拡縮自在“賢い材料”》
【研究で感動を】
現在、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業のACCEL(アクセル)により、製造現場で排ガスとして空気中に放出するCOをより分ける技術開発に取り組む。分離技術にたけた住友精化、鉄鋼生産の工程で大量のCOを出す新日鉄住金らの企業組合で実施中だ。
COは空気中に多い窒素とサイズが似ているため分離が難しい。現状では空中に放出される前に集めて焼却処分している。しかしCOは反応性が高く、うまく分離・濃縮できれば、基礎化学原料として化学会社が活用できる期待がある。
エネルギー源としての主役は19世紀の石炭が固体、20世紀の石油が液体だったのに対し、21世紀は天然ガスや、燃料電池向けの水素など気体だといわれる。濃度が薄く混合しやすいガスにおいて、特定の成分をエネルギーをかけずに分離・濃縮する手だてとして、PCPが期待される。
北川氏は研究の魅力や価値には3段階あり、「科学的な発見という価値だけでなく、人々に驚きを、さらには感動を与える三つ目の段階を目指さなくてはいけない」と強調する。自身の研究でいうと「マスクを通して呼吸するだけで、空気中から濃縮酸素が供給される材料」が一例だ。多くの人に感動を与えることを夢見つつ、研究に取り組む。
(随時掲載)
(2016/11/24 05:00)