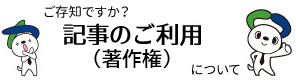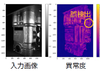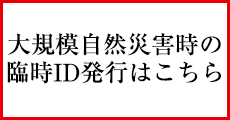- トップ
- 科学技術・大学ニュース
- 記事詳細
[ 科学技術・大学 ]
(2017/5/11 05:00)
東京大学医科学研究所の山梨裕司教授らは、運動機能の低下や筋萎縮を引き起こす「筋萎縮性側索硬化症」(ALS)が、運動神経と骨格筋の接合部を増強する治療によって病態が改善し、延命効果をもたらすことを実証した。マウスの実験で明らかにした。神経筋疾患での神経筋接合部増強という新しい治療法として実用化が期待される。成果は10日、欧州分子生物学機構の科学誌エンボ・モレキュラー・メディシンに掲載された。
運動機能は、運動神経と骨格筋の接合部の構造「NMJ」によって緻密に制御されている。運動神経からの信号はNMJを介して骨格筋に伝わるが、ALSでNMJが変性すると、運動神経が萎縮して骨格筋に運動信号を送られず、運動機能の低下をもたらす。ALSでは呼吸機能の低下などで、約半数が発症後数年で死亡する。
ALSの原因のひとつとしてNMJの形成不全が報告されているほか、NMJの形成にはたんぱく質「Dok―7」が必須であることが知られている。
ALS発症のモデルマウスにアデノウイルス(AAV−D7)によりDok―7の発現を促したところ、NMJの変性と筋萎縮が抑制された。さらに、マウスごとにALSの発症を確認して同様の治療をしたところ、マウスの運動機能低下は改善し、出生後と発症後の生存期間も延長した。
(2017/5/11 05:00)